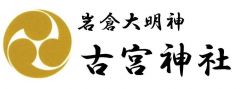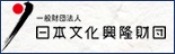お知らせ
2025-11-15 12:00:00

ご家庭の家内安全や各種事業の商売繁盛、厄年のおはらいなど、「新年特別祈願祭」にてご奉仕いたしております。
明年も下記の通り執り行いますので、ご希望の方は12月28日までにWEB・FAXまたは直接社務所へお申し込み下さい。
三が日はすべて予約制としておりますので、それ以外のご希望日はお手数ですがお電話にてお問合せ下さい。
WEB予約はこちらより
(宅配便利用はWEB予約から選択可)
FAX申込用紙はこちらより申込用紙(令和8年).pdf
【1月1日】
①13:30
②15:00
【1月2日】
①10:00
②11:00
③13:00
④14:00
⑤15:00
【1月3日】
①10:00
②11:00
③13:00
④14:00
⑤15:00
初穂料 5千円以上おこころざし
2025-06-23 12:30:00