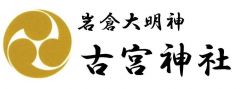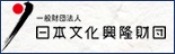お知らせ

古宮神社例大祭が8月28・9日に行われて以降、早1カ月が経過した。緊急事態の発令中で、その後も緊急事態は延長され、9月末までとなった。振り返って見ると、新型コロナウイルス感染者が爆発的に増大した時期で、普段と違った対策をして、例大祭を実施せざるを得なかった。
8月18日に臨時総代会を開催し、本年の例大祭実施方針を協議した。宵宮の夜店などは、昨年同様中止という判断をしていたが、更に感染予防を徹底しないといけないという認識である。そこで祭事係他の祭事参加者は、すべて検温を実施して、密にならない配慮をして、すべての神事を実施することにした。28日午前9時より、疫病退散祈願祭、引き続き神幸祭の発輿祭を行う。疫病退散祈願祭では、疫神除の祈願札(赤札)に祈願をこめて、氏子各戸に配布した。
神幸祭に子供たちの参加は無く、神輿を軽トラックに載せ、獅子舞の太鼓を打ち鳴らして、地区内を巡行し、悪疫退散を祈願した。御旅所での神事は中止して、午前11時に神輿が還御になると、引き続き、例大祭祭典を実施し、ほしのみや保育園園児(年長組)により、朝日舞(男子)、浦安舞(女子)の奉納があった。
保育園園児たちは、春から練習を重ねてきて、当日は感染予防を徹底して、境内の庭上で奉納した。夏の強い日差しを避け、なるべく木陰での奉納となった。翌29日は、神職のみにて神事を行い、滞りなく本年の例大祭を終了した。
彼岸が過ぎ、急速に秋が深まってきた。黄金色に色を変えつつある田んぼの畔に、彼岸花が満開の場所があちこちに見える。天候不順が続いた一年であったが、関東地方は豊作ではないか、と予想されている。有難いことである。改めて、新型コロナ感染症の終息と平穏な日常が戻ることを、祈念したい。
新型コロナウイルス・デルタ株の感染拡大が止まらない。ワクチン接種が進めば感染は自然に鎮静して行くものと思っていたが、未だワクチン接種の進んでいない壮年層、若年層への爆発的感染が続いている。まもなく、古宮神社例祭を迎えることになるが、昨年同様恒例通りの神事・行事は実施できない。2年連続で宵宮の夜店は中止で、神事中心の例祭となる。残念なことであるが、疫病退散の祈りを徹底して、祭祀厳修に一層努めて行きたい。
本日8月24日から9月5日までパラリンピック東京2020が開催される。熱戦が期待されるが、感染予防を徹底して、大会が成功することを祈念して止まない。7月23日から8月8日にかけて、オリンピック東京2020が開催され大成功であった。開催直前まで一部反対運動があり不快な思いもしたが、選手たちの活躍はそうした暗雲を払い、大きな成果をもたらしてくれた。成功の余韻は今も続いていて、スポーツの力の偉大さを実感させてくれている。
日本人選手の活躍は、多くのメダル獲得に繋がり、素直に嬉しい限りであった。入賞した選手に大きな拍手を改めて送りたい。ベストを尽くしたにも拘わらず、好成績に至らなかった選手にも、心からの感謝の心を伝えたい。勝負の世界には、必ず勝者と敗者がある。心を躍らせるドラマが其処のあり、一層の感動があるのであろう。それにしても若人の活躍は、明るい未来の到来を予感させる。多様な社会の中で日本人としての特性を生かして、力を発揮できる人材がたくさんいることに気付かせてくれた。頼もしく、今後一層の活躍を期待したい。
平和の祭典であるオリ・パラ大会が開催されている最中にも拘わらず、世界は激動している。この現実を冷徹に認識し、足元を確りと固めていないと、平安な日常は守れない。気候変動の厳しさは、毎年この時期に続く豪雨災害で、危機意識を更に募らせている。先ずは新型コロナを一日も早く終息させて、平穏な日常を取り戻したい。

本日は6月30日、令和3年も早半年が過ぎ、明日から後半の半年が始まります。今日の夕刻、半年分の罪穢を祓う夏越の大祓を行いました。当社でも6月20日に茅の輪を参道の正面に設け、お参りの人にくぐっていただき、心身を清めていただいて来ました。コロナ禍が続く中、ウイルスを払うだけでなく、蔓延している気うつな気分を、爽やかな風が吹き抜けるが如く、祓え清めたいと祈ります。
国家行事としての大祓は、遠く飛鳥時代に始まっています。奈良・平安時代は国家機構が集まる大内裏の正面の朱雀門の前に、夕刻に百官が集合して、神事を司る中臣が大祓詞を宣読して、御祓を行いました。この国家行事としての大祓式は、中世になると行われなくなり、廃絶してしまいます。
民間ではそのような時でも、茅の輪をくぐり、お祓いをする風が続いていて、おそらく神社社頭などで大祓が続いてきたものと思います。一年を二期に分け、6月晦日と12月大晦日に大祓をする風は、神代以来の仕来りと思われます。
夏越の大祓は、猛暑の中の疫病蔓延防止やお盆の先祖祭前の清め、大晦日の大祓は、正月の神祭りの清め祓えの意味がありました。先祖の生活体験の中から生まれてきた行事です。生活に根差した行事ですので、廃れることがありません。国家行事の大祓はなくなっても、民間に根強く継承されて来た理由がここにあります。必要があったから、行われて来たのです。昨年・今年とコロナ禍にあって、益々そのことを実感します。
宮中では、今日の午後、天皇のお祓である節折(よおり)が行われ、引き続き国民の大祓が行われました。そして全国神社にて大祓が行われ、国中が清められるのです。現行の最大の課題は、コロナ禍の克服です。天神地祇八百万の神々の御神徳により罪穢が清められ、平穏な日常の一刻も早い回復を祈りたいものです。

5月5日、恒例の疫神祭を滞りなく奉仕した。若葉の生い茂る鎮守の森、風薫る好季節で、一年で一番活力にあふれる。境内に立つだけで気持ちのいい時季である。埼玉の県北地域では、種子おろしが行われ、農作業が本格化する。その直前に疫神祭を行い、地区内のお祓いを行い、集落の境にフセギ札を忌竹に挟んで立て、邪神の侵入を防ぎ、豊作を祈るのである。
神社に伝わる獅子舞(獅子頭3頭及びメンカ)が、氏子区域を清めて廻る。奉仕するのは地区内の子供たちであるが、昨年、今年とコロナ禍であるので、子供たちの奉仕は自粛して、行列のお供をしてもらうだけにした。
コロナ禍にあって、疫神祭の意義を改めて考えさせられた。切実な祓えと祈りとで、先祖たちが歩んできたことに思いを致した。昔は氏子各戸の家に入り、土足で座敷まで上がり、家中を清めたのだ。獅子舞が家に入ることで浄化され、疫神の災いを防ぐことが出来ると考えられた。今は大分省略され、獅子舞の太鼓と笛の音で、集落全体を巡り、丁度集落の東西に位置する寺と神社の庭で、獅子舞を舞うことにしている。今年も滞りなく疫神祭の奉仕ができたこと、嬉しく思うと共に、コロナの一日も早い終息を重ねて祈りたい。
今、当地区では農地改善のため土地改良事業を進めている。旧来の小規模の水田から、大規模農地への転換工事を行っている。道路や水路も付け替えられ、大型の農機で耕作可能な水田に姿を変えようとしている。完成すれば、将来は数軒の専業農家で、充分耕作が可能になるだろう。そうしないと耕作放棄地ばかり増えて、明るい未来が描けないのだ。
農業後継者の減少問題は、当地区でも切実である。現役で農業を支えているのは高齢者で、若手の後継者は数えるばかりである。魅力のある農村地帯を維持するのには、どうしたらよいのか。日本全体の問題でもあるが、若い人が農業に魅力を持つ環境を整えなければならない。土地改良が地域の発展に寄与するように願って止まない。